30代で高校教諭(正規雇用)を辞めてセミリタイアした皮算用です。
20年近く2号被保険者をした後、子どものいないDINKs家庭だったこともあり夫の扶養に入り3号被保険者となりました。
夫婦共働き世帯も増えていますがストレスフルな社会なので「扶養内でのんびり働きたい」大人は多いはずです。
考えに考え抜いた(はずの)我が家の体験が参考になればと思います。

社会保険の負担のない3号被保険者ですがざっくり下記2つに分けられます。
- 稼ぎの少ない3号被保険者
- 稼ぎの多い3号被保険者
専業主婦主夫とパート主婦主夫というだけでなく、今どきは各人様々です。
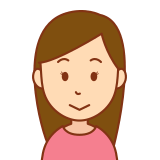
専業主婦だけど株式売買や配当金といった収入があるけど、働いてはない(給与所得はない)から『専業主婦』よね?
『稼ぎの多い3号被保険者』ならばいずれは個人事業主(青色申告)や法人化を考えることとなっていきます。
扶養内の3号被保険者だけど収入を増やしたい!
- 【特定口座・源泉徴収あり】で資産運用する
- 白色個人事業主で経費にする
特定口座・源泉徴収あり

証券会社に口座を作ると数種類口座が選べます。
- 一般口座
- 特定口座・源泉徴収あり
- 特定口座・源泉徴収なし
- NISA口座
- つみたてNISA
一般口座と特定口座・源泉徴収なしの2つは、年間で20万円を超えた収入になると確定申告が必要です。

特定口座・源泉徴収ありは最初から税金が天引きされているので確定申告不要です。
NISAは非課税なので税金の負担がありません。
(確定申告しなくてよい)
確定申告すると他に収入があることが配偶者の健康保険組合にバレます。
ここでパート収入と合計して、年収130万円以上となると3号被保険者から外れてしまいます。
そのため、口座を作るならば特定口座・源泉徴収ありにしておくと安心です。
ちなみに、20万円以下の収入では確定申告の必要はありませんが、住民税の申告は必要です。


知らず知らずに脱税してるとか、恐い!
NISA口座は年間120万円×5年間の運用ですし、マイナスとなった場合に損益通算できないので使い勝手が悪いです。
やるならつみたてNISAですが年間40万円×20年間の運用なので、つみたてNISAだけだと運用利益が少ないです。
3号被保険者名義で資産運用せず配偶者が資産運用しても良いです。収入の少ない3号被保険者側が資産運用するメリットはあります。

白色個人事業主で経費にする
3号被保険者のまま個人事業主として開業できるかどうかは配偶者の所属する社会保険組合で異なっています。

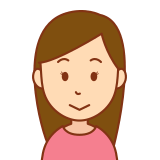
何を経費にするの?
なんて聞かれそうですが、これまたどこまで経費にできるかは配偶者の所属する社会保険組合で異なっています。
- 接待費(食事代)
- 会議費(カフェ代)
- 旅費交通費(本人分の電車・飛行機代)
- 図書費新聞費
- 消耗品(1つ10万円未満)
開業する事業内容によっては自家用車の諸経費も経費計上できる場合があります。





コメント